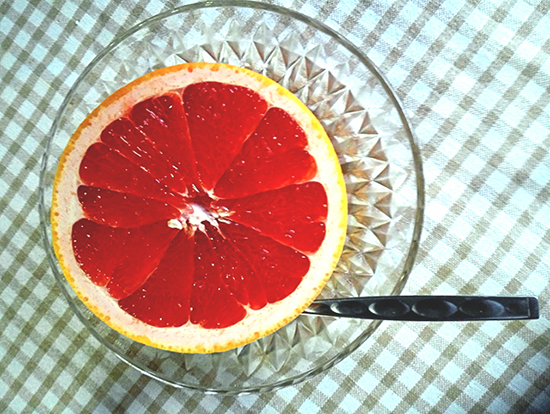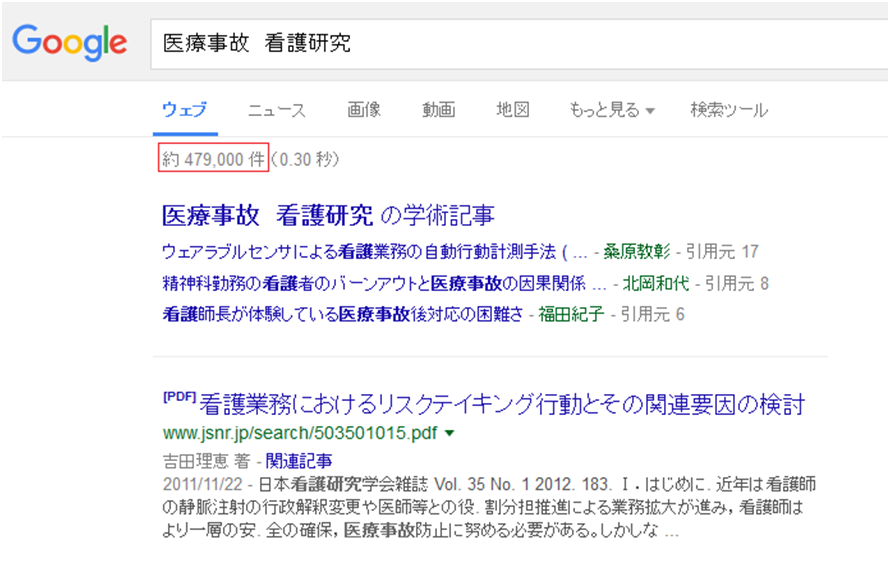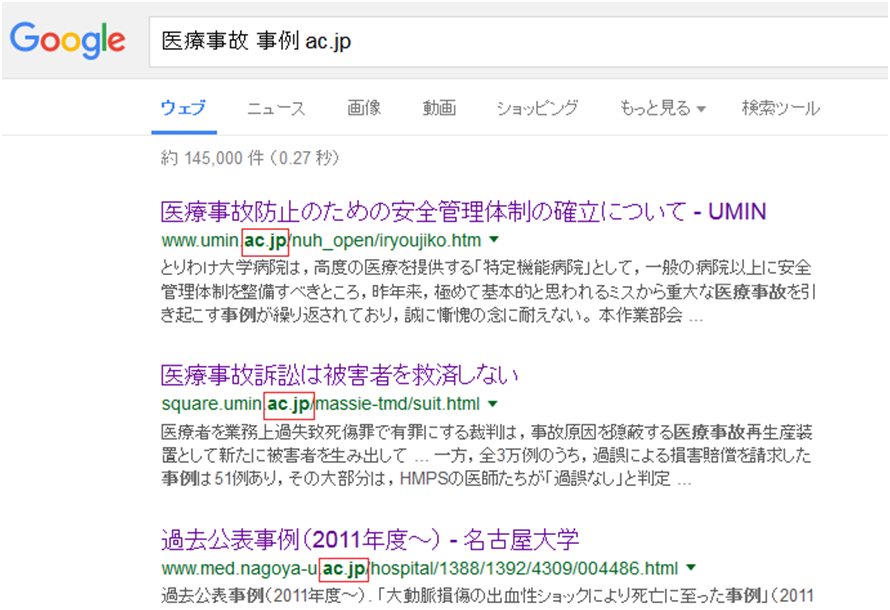看護論を学ぶ過程で、「ケアリング」という言葉が出てきますが、ケアリングというのは看護実践の中核となる概念であり、看護者と対象との関係の在り方を示す重要な概念のことです。
理論や倫理というのは小難しくとっつきにくいものですが、ケアリングは看護実践において無くてはならない概念であるため、この機会にケアリングについてしっかりと学んでください。
当ページでは、ケアとケアリングの違いや、さまざまな人物が提唱したケアリングの概念、ケアリングの本質などについて分かりやすく解説します。
1、ケアリングとは
看護において、看護ケア、緩和ケア、ターミナルケアというように、「~ケア」という言葉がよく使われます。そもそもケアというのは英語で「Care(援助)」のことであり、キュア「Cure(治療)」と異なり看護そのものの事を指します。
では、ケアリングとは何のことなのでしょうか?
ケアリングは英語で「Caring(優しさ、援助する)」と言い、Careの名詞・形容詞ですが、看護におけるケアリングは単なる言葉の延長に止まらず、さまざまな意味合いを持っています。
■ケア・ケアリングの違い
ケア 従来、身体的な世話を言い表す用語として主に使われてきた。身体的な世話により対象者との相互作用が促進されたり、対象者の心身が安楽になったりすることから、「療養上の世話」もしくは「生活の支援」としてのケアに看護の独自性を見出そうとしてきた歴史も長く、看護職にとって重要なキーワードである。また、医療の中では、キュアに対して看護の特徴を際立たせるために、キュア対ケアという構図で用いられる場合もある。 ケアリング 1.対象者との相互的な関係性、関わり合い、2.対象者の尊厳を守り大切にしようとする看護職の理想、理念、倫理的態度、3.気づかいや配慮、が看護職の援助行動に示され、対象者に伝わり、それが対象者にとって何らかの意味(安らかさ、癒し、内省の促し、成長発達、危険の回避、健康状態の改善等)をもつという意味合いを含む。 また、ケアされる人とケアする人の双方の人間的成長をもたらすことが強調されている用語である。 出典:日本看護協会 看護にかかわる主要な用語の解説
つまり、極論で言えば、ケアは「看護師→患者」というように看護師が患者に対して一方的に援助を行うこと、それに対してケアリングは「看護師⇔患者」というように、患者に対して援助を行うことで看護師自身がケアされる(成長する)と考えると分かりやすいのではないでしょうか。
よって、ケアリングは単なるCareが派生した意味合いに止まらず、「Care + Ring(輪)」のように、患者にケアを行うことでその行為が“輪”のように看護師自身に利となって帰ってくるという概念が存在するのです。
なお、これまでに「ミルトン・メイヤロフ」、「マドレイン・M・レイニンガー」、「ジーン・ワトソン」、「パトリシア・ベナー」などによって、ケアリング論が提唱されています。各人によるケアリング論に相違はあるものの、「看護師⇔患者」の関係性における本質に変わりはありません。
2、メイヤロフのケアリング論
メイヤロフは、著書「ケアの本質」の中で、「一人の人格をケアすることは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現することを助けることである。」と述べているように、「他者にケアを行うことで自分自身の成長に繋がる」というケアリングの基本概念を確立した人物です。
また、彼女は同書の中で、ケアリングが行われる一連の過程を以下のように説明しています。
私は他者を自分自身の延長と感じ考える。また、独立したものとして、成長する欲求を持っているものとして感じ考える。さらに私は、他者の発展が自分の幸福感と結びついていると感じつつ考える。そして、私自身が他者の成長のために必要とされていることを感じとる。私は他者の成長が持つ方向に導かれて、肯定的に、そして他者の必要に応じて専心的に応答する。
つまり、メイヤロフが考えるケアリングとは、看護師が患者を尊厳のあるかけがえのない存在として認識し、その上で、看護師が患者のニーズに応えることで患者が成長し、看護師自身もケアを提供することで自身に欠けているものに気づく(成長する)という、他者志向的かつ自己志向的行動で、互いの利における関係性を重視したものなのです。
■メイヤロフが論じるケアの要素
| ①知識 | 誰かをケアするためには、その人がどんな人であるか、その人の力や限界はどの程度か、その人が求めている事は何かなどについて知ること。 |
| ②リズムを変えること | 単に習慣的に行うのではなく、自分の行動のもたらす結果に照らし、次の行動を修正すること。 |
| ③忍耐 | 相手の状況やペースに応じて相手の成長を助けること。 |
| ④正直 | 自分自身に正直に向き合うこと。 |
| ⑤信頼 | 相手の成長と自分自身を信頼すること。信頼が欠如するとケアの成果を求めたり、ケアしすぎてしまう。 |
| ⑥謙遜 | 他者について学び続けること、他者に対してケアすることがまだあることを理解すること。 |
| ⑦希望 | 自分の行うケアを通して相手が成長していくという希望のこと。 |
| ⑧勇気 | 相手がどう成長するのかわからないとき、相手の成長の可能性を信頼すること。 |
これは看護師の側に立ったものですが、これら8つの要素から成る姿勢・態度でケアを行うことで、患者との関係性に相互性をもたらすと論じています。
■ケアの概念の備える特徴
| ①ケアは過程 (プロセス)である | 他者と関わり合うのは 「現在」であるものの、「過去 」 「現在 」 「未来」 という時間の一連の流れ (過程)の中で 「現在」を捉えていくことが重要である。 |
| ②ケアは患者との関わり方(相互関係)である | 人間と人間が出会ったその瞬間から相互交流が始まり、 どのような出会いをするかによって両者の関係は変わっていく。 |
| ③ケアは患者と自己成長を促す ものである | 他者に対するケアを通してその人を成長 ・発展させ自己実現を図るようにすることであり、同時に看護師もまた成長し自己実現を図ることができる。 |
| ④ケアは対象者や場面が変わってもパターンは共通である | ケアには対象や場面がいかに変わろうとも相手の成長 ・発達を助けるという共通のパターンが存在する。 |
3、レイニンガーのケアリング論
レイニンガーはメイヤロフなど先駆者が提唱したケアリング論に、文化人物学の手法を取り入れ、独自のケアリング論(文化ケア論)を提唱し、“ヒューマンケアリングこそが看護の本質である”と述べた最初の人物です。
■レイニンガーが提唱するケアとケアリングの定義
| ケア
=現象 |
人間の状態や生活の仕方を改良、改善するために、明らかにニードのある、またはニードがあると予想される他者に働きかけ、または他者のために経験と行動を助け支援し、できるようにすることに関係した、抽象的なそして具体的な現象を指す。 |
| ケアリング
=行為・活動 |
人の状態や生活の仕方を改良、改善したり、死と立ち向かわせるために、明らかにニードのある、またはニードがあると予想される他の個人や集団を助け、支援し、それができるようにすることに向けられた行為や活動を指す。 |
■ヒューマンケアリングの概念
| 看護を必要としている人々を慈しみ、かけがえのない人間として世話をし、気遣い、理解し、支えること。それは温かな関係作りから始まり、その過程において対象者も看護者も共に成長すること。 |
レイニンガーはヒューマンケアリングの概念(癒し・安寧)が看護の本質であると捉え、メイヤロフが提唱したケアリングの基本概念である「他者にケアを行うことで自分自身の成長に繋がる」という概念に文化的要素を取り入れ、文化的価値・信条・慣習に矛盾しないケアを提供することが第一であると説いています。
4、ワトソンのケアリング論
ワトソンはレイニンガーの理論(文化ケア論)を拡大させ、人間的で哲学的な価値観と科学的な知識を統合し、人間の尊厳や人間性を護ることこそが看護の中心であると考え、独自のケアリング論を提唱しました。
要するに、レイニンガーが考えるヒューマンケアリングを基盤に、「健康」と「癒し」に焦点を当て、人を「尊重する」という概念を重視したケアが、ワトソンが提唱するケアリング論です。
■看護の際のヒューマンケアという価値観に関連した前提
| ①ケアと愛は、最も普遍的・神秘的かつ膨大な規模の宇宙の力である。
②ケアと愛は、見過ごされることがあるが、人間らしさの存続に不可欠である。これらのニードを充足することによって人間性の維持・回復を実現することができる。 ③ケアの哲学と信念を看護の実践場面で生かすことによって、人間発達の文化に影響を与え、また社会に貢献することができる。 ④自分自身をケアし尊重することによって、相手のことを心からケアし気遣うことができる。 ⑤看護は人々の健康一不健康という現象に絶えず関心をはらい、常にヒューマンケアというスタンスをとってきている。 ⑥ケアリングは、看護の本質であり実践の場面においては扇の要のような位置にある。 ⑦ケアリングは、近代医療のシステムの中で重要視されなくなってきている。 ⑧ケアリングの基盤は、バイオテクノロジーの進歩や官僚機構、官僚的制度などによって束縛され脅かされている。 ⑨学問的にも臨床的にも、ヒューマンケアリングの維持・恒常は、今日および将来の看護にとって重要な課題である。 ⑲ヒューマンケアリングは、人と人との「間主観的」なかかわりによって磨かれ実践に生かされる。 ⑪看護は、ヒューマンケアリングの哲学を理論・実践・研究に活用することを通して、人類や社会に対して道徳的・科学的に貢献できる。 |
5、ベナーのケアリング論
ベナーはまず、気遣いや関心を持って接することから始まり、看護を提供する課程で他者と関与し、他者に看護を提供することで自身の意欲向上に繋がり自己研鑽に繋がるという一連の過程がケアリングであると説いています。
つまり、「気遣う看護」をケアリングの実践と捉え、感情や情動といった目に見えない感覚的なものだけでなく、患者の安心・安全・安楽の向上を目的とした治癒過程の促進を目指す看護行為そのものがケアリングであると考えているのです。
■ベナーが考える看護の援助役割
| ①癒しの関係。
②痛みやひどい衰弱に直面した際、安楽にし、その人らしさを保つ。 ③存在する。 ④患者が自分自身の回復の過程に参加し、コントロールすることを最大にする。 ⑤痛みの種類を見極め、適切な対処方法を選んで、痛みの管理やコントロールを行う。 ⑥触れることを通して安楽をもたらし、コミュニケーションを図る。 ⑦患者の家族に情緒的なサポートと情報提供的サポートを行う。 ⑧情緒的・発達的なサポートを通じて患者を導く。 |
これらの役割を果たすことで、看護師自身がさまざまな状況に対応できる援助法を得ようという意欲、失敗を恐れず挑戦しようという意欲、援助役割を自分のものにしようという意欲がかき立てられ、看護師の自己研鑽に繋がるというのがベナーが説くケアリング論です。
6、各人のケアリング論の共通性
ここまで、「メイヤロフ」、「レイニンガー」、「ワトソン」、「ベナー」の4人のケアリング論をご紹介しましたが、それぞれに独自の概念が存在するものの、ケアリングの根本となる4人の共通概念が存在します。この共通概念は、“ケアリングとは何か”を厳密に示したもので、ケアリングの本質がここに見えてきます。
| ①ケアリングは看護師―患者間に存在する。
②ケアリングは看護において重要であり、 なくてはならないものである。 ③ケアリングは、患者の目的達成を目指す過程で発揮される。そこでは看護師の成長も達成される。 ④ケアリングは、その過程や発揮された場面が非常に見えづらく、わかりにくいものである。 |
このように、看護師と患者との関係性の中で生まれ、患者にケアを提供することで看護師自身が成長できるという概念がケアリングなのです。
7、引用文献
1)ミルトン・メイヤロフ.(1993).ケアの本質;生きることの意味,田村真・向野宣之訳.ゆみる出版.
2)マデリン M. レイニンガ-著、稲岡文昭監訳、「レイニンガ-看護論~文化ケアの多様性と普遍性」 、医学書院.
3)Watoson J (1988) 稲岡文昭監訳 (1992):ワトソン看護論一人間科学とヒューマンケア,医学書院,束京,109-110.
4)Patricia Benner, 井部俊子他訳:ベナー看護論:達人ナースの卓越性とパワー, 医学書院, 1998.
まとめ
ケアリングは、“輪”のように看護師・患者の双方が関係を成し、ケアする者とケアされる者が互いに成長できる理論であるため、たとえば、医療現場では「看護師⇔患者」だけでなく「看護師長⇔看護師(スタッフナース)」や、「教師⇔生徒」といった教育現場においても当てはまります。
患者のQOL向上のため、予防や早期治療のために何ができるかを常に考えることで、一方的なケアに止まらず自身の成長にも繋がります。
この機会に一方的なケアから双方が利となるケアリングの概念を心に留め、患者によりよい看護ケアを提供すると共に、自己研鑽に励んでいってくださいね。